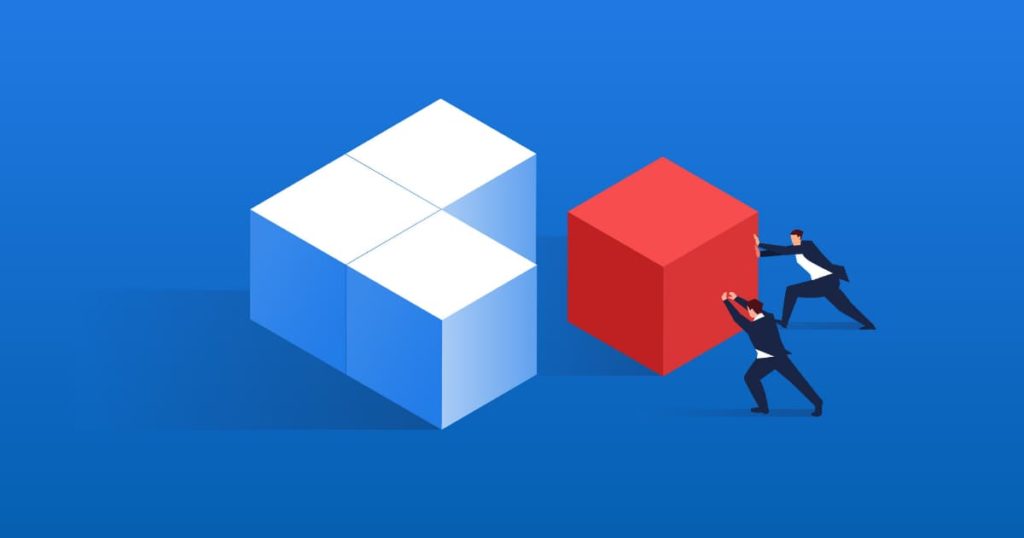金融検査マニュアルが廃止になったからっていっても、そんなにすぐに銀行の実務が事業性評価融資に全面的に移行するわけはないだろうし、まだまだこれからも金融検査マニュアルの考え方は影響を残すのだろう。
銀行が提示してくる金利は債務者区分と大きな関係があるようだし、その債務者区分を決めていたのが金融検査マニュアルだったそうなのだが、債務者区分の考え方を詳しく教えてほしい。
債務者区分をしっかり知っておくことで、銀行と金利交渉も上手くいきそうな気がする。
債務者区分の考え方を知っておくことで、自社の債務者区分が理解でき、銀行との様々な交渉がしやすくなることは確かですね。
そこでこの記事では、債務者区分の基本的な考え方をじっくり説明していきますね。
この記事を読むことで、債務者区分の基本的な考え方がしっかり理解できて、銀行との様々な交渉に役立ちます。
本記事は20年以上に渡って中堅・中小企業の事業再生に関わり、200件以上の事業再生案件に関与して、マーケティングと管理会計と組織再編の力で再生に導いてきた事業再生のプロである公認会計士が書きました。
債務者区分が貸出金利を決める
 銀行が融資を実行するにあたって、調達金利に事務費用等と融資先のリスクに応じたリスク・プレミアムを乗せて、最終的な貸出金利を決めています。
銀行が融資を実行するにあたって、調達金利に事務費用等と融資先のリスクに応じたリスク・プレミアムを乗せて、最終的な貸出金利を決めています。
このリスク・プレミアム相当がスプレッドと呼ばれるものであり、それは債務者区分によって決定されていることになります。
したがって、自社の金利水準が高いか低いかを考える際には、自社の債務者区分は何のかを知る必要があり、自社の債務者区分が概ね理解できれば、金利を交渉する時に非常に役立つことになります。
2019年12月で金融検査マニュアルが廃止され、今後は事業性評価融資が融資実務の中心となっていくと予想されますが、依然として金融検査マニュアルに沿った債務者区分およびそれをベースにして貸出金利の考え方は金融実務の中心となっています。
したがって、金融検査マニュアルに基づく債務者区分の考え方はまだまだ重要ということになります。
「金融検査マニュアル」の詳細については下記の記事を参考になさってください。
金融検査マニュアルが廃止になったそうだが、我々のような中小企業に対する銀行の融資姿勢は変わるのだろうか。また、貸し渋りや貸しはがしのようなことが起こるんじゃないだろうね。金融検査マニュアルの廃止が与える影響を知りたい方のために書きました。
「金融検査マニュアル別冊【中小企業融資篇】」についての詳細は下記の記事を参考になさってください。
金融検査マニュアル別冊は中小・零細企業向けに策定されたものだが、中小企業経営者の私もその内容についてはよく理解できていない。どんな視点で評価されているのかを知ることで、今後当社が実施するべきことが明確になるはずだ。こんな悩みに回答します。
債務者区分は自己査定で決まる
 金融機関が行う資産査定とは、金融機関の保有している資産(その中心は貸出債権)を個別に検討して、将来それが回収できるかどうかの度合いに従って区分することであり、預金者の預金などがどの程度安全確実な資産に見合っているか、言い換えれば、資産の不良化によりどの程度の危険にさらされているかを判定することをいい、金融機関自らが行う資産査定を自己査定といいます。
金融機関が行う資産査定とは、金融機関の保有している資産(その中心は貸出債権)を個別に検討して、将来それが回収できるかどうかの度合いに従って区分することであり、預金者の預金などがどの程度安全確実な資産に見合っているか、言い換えれば、資産の不良化によりどの程度の危険にさらされているかを判定することをいい、金融機関自らが行う資産査定を自己査定といいます。
自己査定は、金融機関が信用リスクを管理するための手段であるとともに、適正な償却・引当を行うための準備作業となります。
また、償却・引当とは、自己査定結果に基づき、貸倒等の実態を踏まえ債権等の将来の予想損失額等を適時かつ適正に見積ることをいいます。
金融機関からすれば、融資先に融資している貸出債権は資産であり、預金者から集めた預金は負債となります。
預金は負債ですから、法律的には返済する義務を負いますが、その返済原資としての資産がしっかりと存在していないと預金者への支払が不能となってしまいます。
したがって、預金に見合う資産が存在することを自己査定でしっかりと確認する必要があるのです。
金融機関の資産の多くは貸出債権ですから、これが将来、債務者からきちんと返済されるのかどうかを定期的にチェックする必要があり、万が一、融資先に有した貸出債権の貸倒れが続けば銀行は破綻し、銀行が破綻すれば預金の安全性も脅かされてしまいます。
そこで、貸出先である債務者の業況などを把握して、融資した資金が返済できなくなるリスク(これを回収の懸念、信用リスクなどと表現します)を銀行自身が見極めなければならず、このように自らが所有する債権を査定することを自己査定と呼ぶのです。
基本的な考え方
 金融検査マニュアル別表によれば、
金融検査マニュアル別表によれば、
「債務者区分」とは、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を判定して、その状況等により債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先 に区分することをいう。
自己査定の方法は、各々の金融機関が独自のマニュアルを策定・実施しているので、詳細な部分では当然に異なってきますが、金融検査マニュアルでは次のように債務者区分を判断するように求めています。
債務者区分は、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力等により、その返済能力を検討し、債務者に対する貸出 条件及びその履行状況を確認の上、業種等の特性を踏まえ、 事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローによる 債務償還能力、経営改善計画等の妥当性、金融機関等の支援 状況等を総合的に勘案し判断するものである。
特に、中小・零細企業等については、当該企業の財務状況 のみならず、当該企業の技術力、販売力や成長性、代表者等 の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産 内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の 経営実態を踏まえて判断するものとする。
これらを要約すれば、債務者区分にあたっては、基本的には次の3つのポイントをチェックしていくことになります。
- 収益性はどうか・・・黒字かどうか
- 財務内容の状況・・・実質債務超過に陥っていないか
- 返済能力の有無と返済状況・・・返済状況に問題がないか(返済原資が確保できているか)
これに加えて、要注意先以下の会社には、必要に応じて経営改善計画や他の金融機関の支援状況などについても考慮していくことになります。
さらに、財務基盤が脆弱な中小・零細企業においては、中小企業の特性に鑑みて、形式的に金融検査マニュアルを当てはめて債務者区分を決定しないように求めています。
その詳細については、「金融検査マニュアル 中小企業融資篇」に記載されています。
「金融検査マニュアル別冊【中小企業融資篇】」についての詳細は下記の記事を参考になさってください。
金融検査マニュアル別冊は中小・零細企業向けに策定されたものだが、中小企業経営者の私もその内容についてはよく理解できていない。どんな視点で評価されているのかを知ることで、今後当社が実施するべきことが明確になるはずだ。こんな悩みに回答します。
収益性の判断
債務者区分を実施するにあたって、収益性は大きな判断要素となります。
要するに赤字か黒字なのかということですが、黒字であれば債務を返済する可能性はぐっと高まりますが、赤字であればそうでなくなります。
また、赤字であるからという理由で短絡的に債務者区分が正常先でなくなるわけでもなく、次のような場合には、決算が赤字であっても正常先になる可能性は十分にあります。
①創業赤字で当初の事業計画と大きな乖離がない場合
会社の創業時は、創業準備費用や開業準備費用等の、創業時ならではの特別な費用が計上される可能性が多く、その結果、赤字となる可能性が高いのが普通です。
このため、当初計画した売上等が概ね7割を達成している形で赤字になっていても、黒字化まで概ね5年以内の計画であれば、正常先と判断することになります。
ここでいう赤字とは最終損益段階の出の赤字を指しており、創業費用や開業準備費用などの臨時的な費用の発生で最終損益が赤字になる場合ということで、本業の収益性を示す営業段階では、創業時であっても黒字が求められます。
もちろん創業時なので、営業赤字であってもその将来的な収益性を勘案して正常先である可能性は十分にあります。
②赤字が一過性のものであり、短期間で解消が可能である場合
①の場合と同様に、赤字の原因が所有不動産等の固定資産の売却損など一過性のものである場合には、正常先と判断することができます。
他にも、固定資産等の減損損失の計上や有価証券評価損の計上など、一過性の減益要因がある場合に、これを受けて一時的に赤字に転落したから直ちに要注意先に債務者区分を下げるのは、適切に債務者区分を実施できていることにはならないでしょう。
もちろん、この赤字も①と同様に最終段階による赤字を想定していますので、①のケースと同様に、営業損益・経常損益の段階では黒字であることが前提だと考えるべきです。
③債務の返済能力に疑義がない場合
これ以外にも、赤字ではあるのだけけれども、キャッシュ・リッチであったり、所有資産の売却によって返済原資を十分に確保できるなど、返済能力には特に問題ない会社であれば、赤字であっても正常先となる可能性があります。
結局、債務者区分で大切なのは、負担する債務を返済することができるかどうかなので、その1つの指標として、収益性の判断を行っていると考えているにすぎないからです。
ここを誤解して、単に収益性等の1つの指標をもって形式的に債務者区分を行うことは避けなくてはなりません。
また、中小・零細企業の場合には、その特性にしたがって、経営者の財産状況等を債務者と一体に査定しなければなりません。
以上、債務返済能力のうちの1つの指標である収益性の判断におけるポイントを書きました。
債務者区分は、収益性だけでなく、下記に記載する他の事項をも考慮して総合的な判断によってなされるものですから、その点はご注意ください。
財務内容の状況
財務内容の状況の検討とは、その会社が実質債務超過に陥っているかどうかを判断するものです。
日々行われる経済的取引を集積した結果として、決算書(貸借対照表、損益計算書等)が作成されますが、それはあくまで財務会計の大原則である「取得原価主義」に基づいて行われたものです。
過去に購入したものや製造したものの時価が下落しているのであれば、その時価の下落分を適切に財務会計に反映させねばなりません。
そうしないと貸借対照表等が経済的実態を表さないからです。
そこで、過去に取得した不動産や株式の時価が下落していれば、減損損失を認識しなければなりませんし、商品在庫が滞留して販売可能性がないのであれば、ゼロまで減損損失を認識しなければなりません。
このように資産負債を時価で評価しなおすことが必要で、そのようにして作成された貸借対照表を実態対貸借対照表といいます。
帳簿ベースでは資産超過であっても、実態ベースでは債務超過に転落するケースはとても多いのです。
実質債務超過は、資産よりも負債のほうが大きい状態ですので、資産をすべて売り払って換金し、それを負債の返済に充当しても、返済しきれない状態を意味しますから、債権者としてそのような会社にお金を貸すことはとてもリスクが高いわけです。
また、実質債務超過にある会社は、少数の例外を除き収益性も低いのが一般的なので、その負担している債務の返済能力も低いと考えるのが普通です。
こうした会社の場合は、貸付金は貸倒れる可能性が高くなるので、債務者区分は低くなるのが通例です。
もちろん、自己査定は収益性やキャッシュ・フローによる償還能力など、総合的な判断の結果なされるので、実質債務超過だけで債務者区分が低くなることはありません。
なお、実際には多くの金融機関は、実質債務超過の解消期間を債務者区分を実施する際の1つの指標として用いています。
解消期間が概ね5年以内であれば、破綻するリスクは低くなるので、要注意先に留まる可能性もありますし、同様に1年以内であれば正常先に留まる可能性もあります。
債務超過についての詳細は下記に記事を参考になさってください。
事業再生において債務超過はどのように取り扱うべきでしょうか。債務超過は銀行の債務者区分に影響を与える要素の1つなので、事業再生にあたり解消する、もしくは圧縮することをテクニカルに考えるべきです。こういったことをケアできる専門家は貴重です。
償還能力の有無と債務の返済状況
償還能力の有無
償還能力の有無とは、債務者が負担している有利子負債について、キャッシュ・ベースでそれを返済する能力があるかどうかということです。
損益ベースの収益性も、財務内容の状況(実質債務超過か否か)も、償還能力を図るための1つの指標ではありますが、金融機関からすれば貸し付けたお金が返ってくるのかどうかがもっとも大事ですので、言ってしまえば、収益力がどんなに低くても、どれだけ実質債務超過がひどくても、償還能力が高ければ問題ないのです。
一般的には、収益力、財務状況と償還能力との間の相関係数は高く、収益力が低く、財務内容が悪化している企業は、この償還能力も低い場合が多いのです。
一方で、たとえ収益力が高いとしてもキャッシュを稼げていないケースでは、延滞や貸倒れる可能性が高くなりますので、銀行は債務者区分を下位に評価せざるを得なくなります。
債務の償還能力の判定式は、各金融機関によって多少異なりますが、概ね次の債務償還年数の算定によって把握することが一般的です。
債務償還年数
= (要償還債務-現預金) ÷ 営業キャッシュ・フロー
= (有利子負債-運転資金-現預金) ÷ (経常利益 + 非現金支出費用-法人税等)
(注):非現金支出費用とは、現金の支出を伴わない発生費用をいいます。
たとえば、減価償却費や退職給付費用、貸倒引当金繰入額などです。実務上は、簡便的に減価償却費のみで計算することが一般的です。
分子の要償還債務は具体的に有利子負債になるわけですが、有利子負債には運転資金も含まれているのが通常ですので、運転資金相当額(売掛債権+棚卸資産-買掛債務)を減額します。
また、営業活動に役立たない余剰資産は売却して債務の返済に充当することができますが、具体的にどれが余剰資産なのかは、貸借対照表からは判明しないので、一般的には現預金のみを控除対象とします。
次に分母のキャッシュ・フローですが、営業キャッシュ・フローを用います。
営業キャッシュ・フローは、厳密には、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を用いるべきですが、実務上は簡易的に、経常利益+減価償却費-法人税等で計算します。
減価償却費以外の重要な非現金支出費用があればこれも考慮します。
この計算式によって得られた債務償還年数の長短によって債務者区分が変わってきます。
概ね次のような年数と区分を使うのが一般的です。
| 債務償還年数(年) | 区分 |
| 10年未満 | 正常先 |
| 10年以上20年未満 | 要注意先 |
| 20年以上 | 破綻懸念先以下 |
倉庫業、ホテル業、不動産賃貸業などは初期投資が大きい業種になりますので、借入金での調達額も大きい分、上記の一般的な指標で債務者区分をしてしまうと、全てが破綻懸念先以下に区分されてしまいますので、こういった業種では、20年~30年くらいの債務償還年数を正常先に区分することになります。
債務の返済状況
償還能力は、今後の債務の償還能力を現在のデータに基づいて予想するものですが、実績としてきちんとお金を返済してきたかも当然問題となります。
債務の返済状況の確認は一般的には、「延滞状況の有無」で行われています。
金融検査マニュアルによれば、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞している債務者を要注意先とし、その延滞期間が3か月を超えれば要管理先、さらに6か月以上延滞している場合には「実質的に長期間延滞している」として、実質破綻先として規定しています。
この金融検査マニュアルの考え方にしたがって、多くの銀行では延滞期間によって、要注意先から実質破綻先に債務者を区分しています。
もちろん、この延滞期間は各々の金融機関によって異なります。
延滞期間と債務者区分の関係は、概ね次のようになるのが一般的です。
| 延滞期間 | 債務者区分 |
| 3か月以下 | 要注意先 |
| 3か月以上6か月未満 | 要管理先・破綻懸念先 |
| 6か月以上 | 実質破綻先 |
要管理先は、要注意先の債務者のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務者のことであり、ここで要管理債権は、3か月以上延滞している債権が該当します。
このため、概ねの目安として、3か月以下が要注意先、6か月以上が実質破綻先で、その間が要管理先もしくは破綻懸念先となると考えて差し支えないということになります。
上記で示した基準も、一般的な指標であり、実際には各銀行で異なりますのでご注意ください。
経営改善計画の効果
破綻懸念先に分類された債務者の場合、債務超過の解消が早期に実現しそうになかったり、借入金の元金返済や利払いが延滞されたりするのが通常ですので、このまま放置することになれば、さらに悪い状態に陥って、実質破綻先や破綻先へと債務者区分が下方遷移し、倒産することも時間の問題となります。
そこで、このようなことを避けるために、破綻懸念先に対しては、金融機関がイニシアティブをとって、経営改善計画を策定し、計画に基づいて種々の施策を実行するのが一般的です。
そして、金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が 策定されている債務者については、以下の全ての要件を充たしている場合には、経営改善計画等が合理的であり、その実現可能性が高いものと判断して、当該債務者は要注意先と判断して差し支えないものとしています。
- 経営改善計画等の計画期間が原則として概ね5年以内で あり、かつ、計画の実現可能性が高いこと。
ただし、経営改善計画等の計画期間が5年を超え概ね10年以内となっている場合であれば、実績(売上および当期利益)が計画の概ね8割以上を確保できていれば問題ないものとしています。 - 計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が原則として正常先となる計画であること。
ただし、計画期間終了後の当該債務者が金融機関の再建支援を要せず、自助努力により事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合は、計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が要注意先 であっても差し支えないものとしています。 - 全ての取引金融機関等において、経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を経て合意されていることが文書その他により確認できること。
- 金融機関等の支援の内容が、金利減免、融資残高維持等 に止まり、債権放棄、現金贈与などの債務者に対する資金提供を伴うものではないこと。
ただし、経営改善計画等の開始後、既に債権放棄、現金贈与などの債務者に対する資金提供を行い、今後はこれを行わないことが見込まれる場合、及び経営改善計画等に基づき今後債権放棄、現金贈与などの債務者に対する資金提供を計画的に行う必要があるが、既に支援による損失見込額を全額引当金として計上済で、今後は損失の発生が見込まれない場合を含むものとしています。
以上の4つの要件を満たしていれば、経営改善計画は合理的で実現可能性が高いものと判断して、当該債務者は要注意先に留めおくことが認められています。
ただし、これらの要件を満たさないからといって直ちに債務者を破綻懸念先に落とすことはあってはならず、債務者区分の検討は、業種等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の妥当性、金融機関等の支援状況等を総合的に勘案して行うものとしています。
特に、中小・零細企業等については、必ずしも経営改善計画等が策定されていない場合があるので、経営改善計画書がないことを理由に破綻懸念先に落とすことがないように注意喚起を図っています。
中小・零細企業に特有の経営実態を総合的に勘案して債務者区分を判断するように求めているのです。
実抜計画と合実計画については、下記の記事を参考になさってください。
実抜計画と合実計画という2つの経営改善計画があるらしいが、各々どのような違いがあるのか、また、どんな場面でその策定が求められるのか、さらには、これらの計画を策定することで何かメリットがあれば合わせて教えてほしい。こんな疑問にお答えします。
経営改善計画書についての詳細は下記の記事を参考になさってください。
経営改善計画書の策定を銀行から依頼された。経営改善計画書に何を書けばいいのか見当がつかないが、いい加減なものを提出して銀行の心証を悪くしたくないし、かといって必要以上に時間をかけたくない。この記事を読むと、必要最低限の記載事項がわかります。
経営改善計画策定支援事業という制度があるらしく、銀行にリスケなどの条件緩和などを依頼する時に必要な計画の策定を外部の専門家に依頼すれば、専門家費用を補助してくれるらしい。この事業について、もっと深く教えてほしい。こんな悩みに回答します。
経営改善計画書のサンプルなどを示しつつ、計画書に記載するべき事項について、どのように考えるべきなのかのポイントや注意点などがあれば教えてほしい。しっかりした計画書を提出しないと、リスケなどに応じてもらえないかも。こんなお悩みに回答します。
3つの決定要素
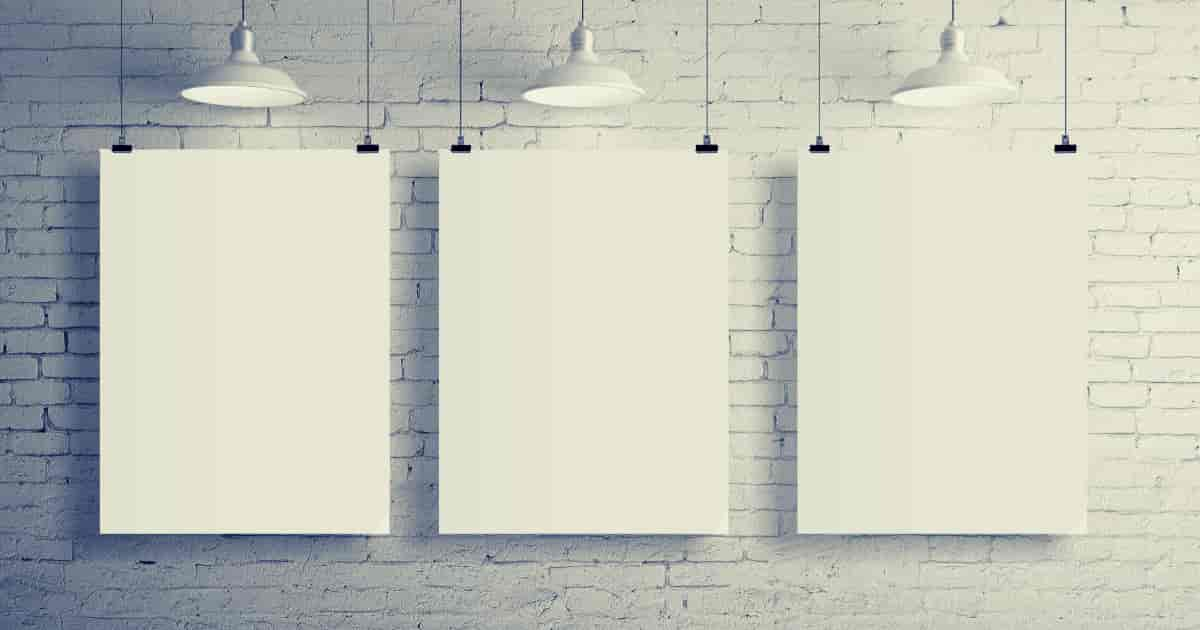 以上のように、金融検査マニュアルにおける債務者区分の決定方法については、①収益性はどうか(黒字かどうか)、②財務内容の状況(実質債務超過に陥っていないか)、③返済能力の有無と返済状況(返済状況に問題がないか)を基本に考えていくことになります。
以上のように、金融検査マニュアルにおける債務者区分の決定方法については、①収益性はどうか(黒字かどうか)、②財務内容の状況(実質債務超過に陥っていないか)、③返済能力の有無と返済状況(返済状況に問題がないか)を基本に考えていくことになります。
この3つの要素を基本に考えながら、要注意先以下の会社については、必要に応じて経営改善計画や他の金融機関の支援状況などについても考慮していくことになります。
さらに、財務基盤が脆弱な中小・零細企業においては、中小企業の特性に鑑みて、形式的に金融検査マニュアルを当てはめて債務者区分を決定しないように求めており、その取扱いの詳細については、「金融検査マニュアル 中小企業融資篇」に記載されています。
「金融検査マニュアル別冊【中小企業融資篇】」についての詳細は下記の記事を参考になさってください。
金融検査マニュアル別冊は中小・零細企業向けに策定されたものだが、中小企業経営者の私もその内容についてはよく理解できていない。どんな視点で評価されているのかを知ることで、今後当社が実施するべきことが明確になるはずだ。こんな悩みに回答します。
こういった基本的な考え方を用いて債務者区分を実施し、6つの債務者区分に債務者を区分するわけですが、各々の債務者区分の詳細については下記の記事を参考にされてください。
金融検査マニュアルの債務者区分は具体的にどのように債務者を区分していたのかを詳しく教えてほしい。また、マニュアルは廃止されたけれど、その後の債務者の区分はどのように変わるのかを教えてほしい。今後の銀行交渉にも大きく関係するだろうからね。
また、金融庁は金融検査マニュアル廃止後は事業性評価へと金融行政の舵を大きく切っています。
ここまでの基本的な債務者区分の考え方に、事業性を評価して最終的に債務者区分等が決定される傾向が今後どんどん強くなります。
事業性評価の詳細については下記の記事を参考にされてください。
事業性評価なるものが、金融検査マニュアルの廃止に伴って金融行政の前面に躍り出てきたけれど、事業性評価っていったい何なのか、また、それは中小企業経営にとって役立つものなのか、役立つのなら何をするべきかも教えてほしい。こんなお悩みに回答します。